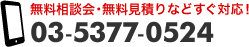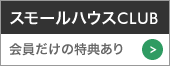狭小住宅を建てる上での高さ制限など、各種制限について
狭小住宅が得意なスモールハウスですが、どのようにして各種の法的制限などをクリアして、狭小住宅を建てているのでしょうか?
一般的には敷地面積が、10坪~20坪位に家を建てる場合は、建物は狭小住宅になります。
まずは考えうる建築基準法による制限に関して。
- 道路斜線制限に関して
- 北側斜線制限に関して
- その他の制限に関して
- 上記の制限をクリアする方法に関して
以上の4点に関して、概略を見ておきましょう。
道路斜線制限とは?
建物を建てる場合には、北側斜線と同様に接道する道路に対しても、建物の高さ制限が存在します。これは道路の通風とか採光を確保するための法的制限になります。
具体的には、敷地に面した道路の反対側にある境界線、かつ道路の中心線からの高さ・ここから一定の勾配で敷地に向かって引いた線が道路斜線になります。
住居系地域では、1対1.25の勾配で、商業系地域では、1対1.5の勾配で作る直角三角形の角度になります。
北側斜線制限とは?
建築基準法によると、第1種,第2種低層住居専用地域・第1種、第2種中高層住居専用地域に対して適用される。
具体的には北側の隣地境界線に一定の高さ5m、10mを取り、そこから北側斜線に勾配がスタートすることになります。
この勾配とは底辺1に対して、高さが1.25の比率となります。
この高さ制限により、北側に住む人の日当たりを確保することになり、こちら側の建物の高さが調整されることになります。
その他の制限に関して
用途地域による制限ですが、新築に際して、当該の地域がどうなるか、建ぺい率、容積率が指定されております。
例えば、防火地域では、(商業系の地域)3階建て以上の建物は、木造建ては禁止されております。構造的には、鉄骨造かRC造が原則になります。但し、木造耐火建築による例外もございますが、コスト的には、高くつきます。
これらの制限も与えられた環境をいかに保全するという観点から考えたものになります。
上記の制限をクリアする方法に関して
- セットバックによる緩和
- 前面道路の反対側に公園とか広場,川などがある場合の緩和措置
- 2面道路に面している場合には、狭い道路に関しては緩和措置がとれる
- その他、建築家において、設計デザイン上考えうる方法
高度斜線の制限に関して
都市部においては、高度斜線の制限が独自に設けられております。それは一般的には建築基準法よりも、より厳しい制限になります。
天空率による緩和に関して
天空率とは魚眼レンズで天空を同心円状に見上げた時、建物を立体的に映した範囲を除いてどれだけ空が見える割合が残るかを示したものです。
これは狭小住宅にとっては、とても有効な設計手法になります。